皆さんは、クラシック音楽を聴く際、どのように楽しみながら聴いていますか?
私が思うに、クラシック音楽の聴き方には2つの楽しみ方があると思いますので、今日はその情報を共有したいと思います。
技術的鑑賞(テクニカル重視)
まずは、技術的な側面を重視した音楽鑑賞をご紹介したいと思います。
例えば、「この楽曲の第4楽章の第1主題の作曲背景は~」とか、「今日のオーケストラの配置は~」とか、「ホルンとクラリネットの協奏が出色で、その後の合奏にこんな影響が~」とか、演奏技術に着目した鑑賞方法です。
楽器演奏の方やマニアの人、スコアを読める人は、こういう音楽鑑賞をすることが多いでしょう。
事前に勉強をする必要がありますが、見方が広がるので、楽しさに拍車がかかる鑑賞スタイルです。
感覚的鑑賞(インスピレーション重視)
一方で、感受性を重視する鑑賞方法もあります。
ようは、「私はこの楽曲からどのようなインスピレーションを受けられたか」という点を重視しながら聴くスタイルです。
このスタイルの良いところは、楽曲の予習が不要であり、かつ、自分との対話が主となるので先入観なくまっさらな気持ちで曲を聴けるという点です。
先の技術的鑑賞をする人でも、初めて聴く曲や難曲の場合、このような聴き方をする時があると思います。
結局どっちがいいの?
では、これら2つの楽しみ方のうち、どちらが良いのでしょうか?
結論から言うと、どちらでも良いと思います。
結局、音楽鑑賞は趣味なので、好きなようにしてもらえればそれで良いのです。
音楽を職業にしている音楽評論家の場合は、そういう訳にはいかないのでしょうが、音楽ファンの聴き方は自由で良いのです。
どちらが偉いとか、そういうことはありません。
ただ、技術的な側面を踏まえつつ、感覚的に聴くと、目の前の世界が広がるかもしれません。
ここから先は、マニアックな領域になってきますので、興味のある方はぜひ、トライしてみてください。
おわりに
以上紹介した2つの鑑賞方法ですが、これは音楽に限らず、美術鑑賞全般でも言えるのかもしれません。
あなたが美術館に行ったとき、絵画に詳しい人は、作者の生涯と作品を照らし合わせたり、タッチや作風を見たりする(ので)しょう。
逆に、何も考えず、その作品をじっと見つめ、作品と自分とが対話をする。インスピレーションを受ける。そんな美術鑑賞をする人もいることでしょう。
私はコンサートホール以外では美術館に足を運ぶ機会が多いので美術鑑賞もしていますが、もっぱら後者の鑑賞スタイルです。
なぜならば、絵画などの展示物の知識がないからです。
でも、それで良いのですよ。
この作品から何か一つインスピレーションを受けられればそれでよしとする、そんな感覚で楽しんでいます。
こういった視点から鑑賞できると、比較的難解とされる現代アート(現代音楽も?)であっても、鑑賞体験を楽しむことができます。
芸術作品には作者の想いが詰まっているのが普通ですから、感受性に意識を向けると、専門知識がなくても芸術作品を楽しむことができるようになると思います。
今度、美術館やコンサートホールで、試しにやってみてください。
「ただなんとなく見る」「ただなんとなく聴く」というのは、あまり面白くないでしょうからね。
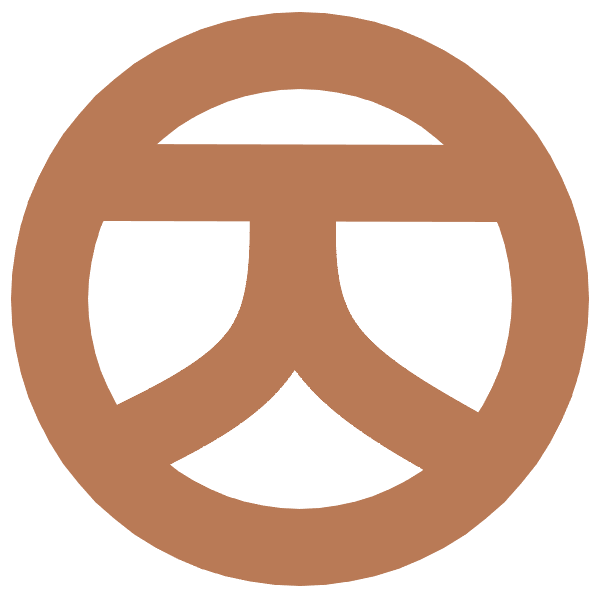 音楽新都心
音楽新都心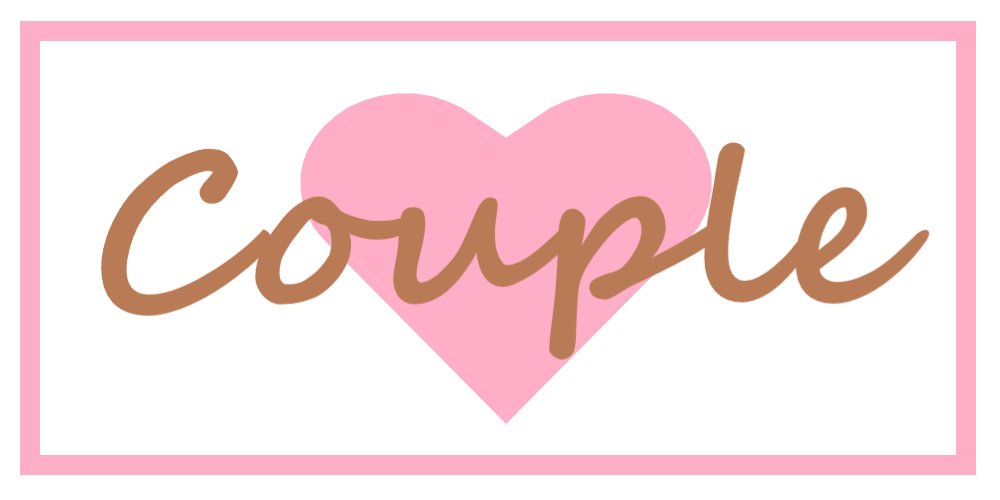


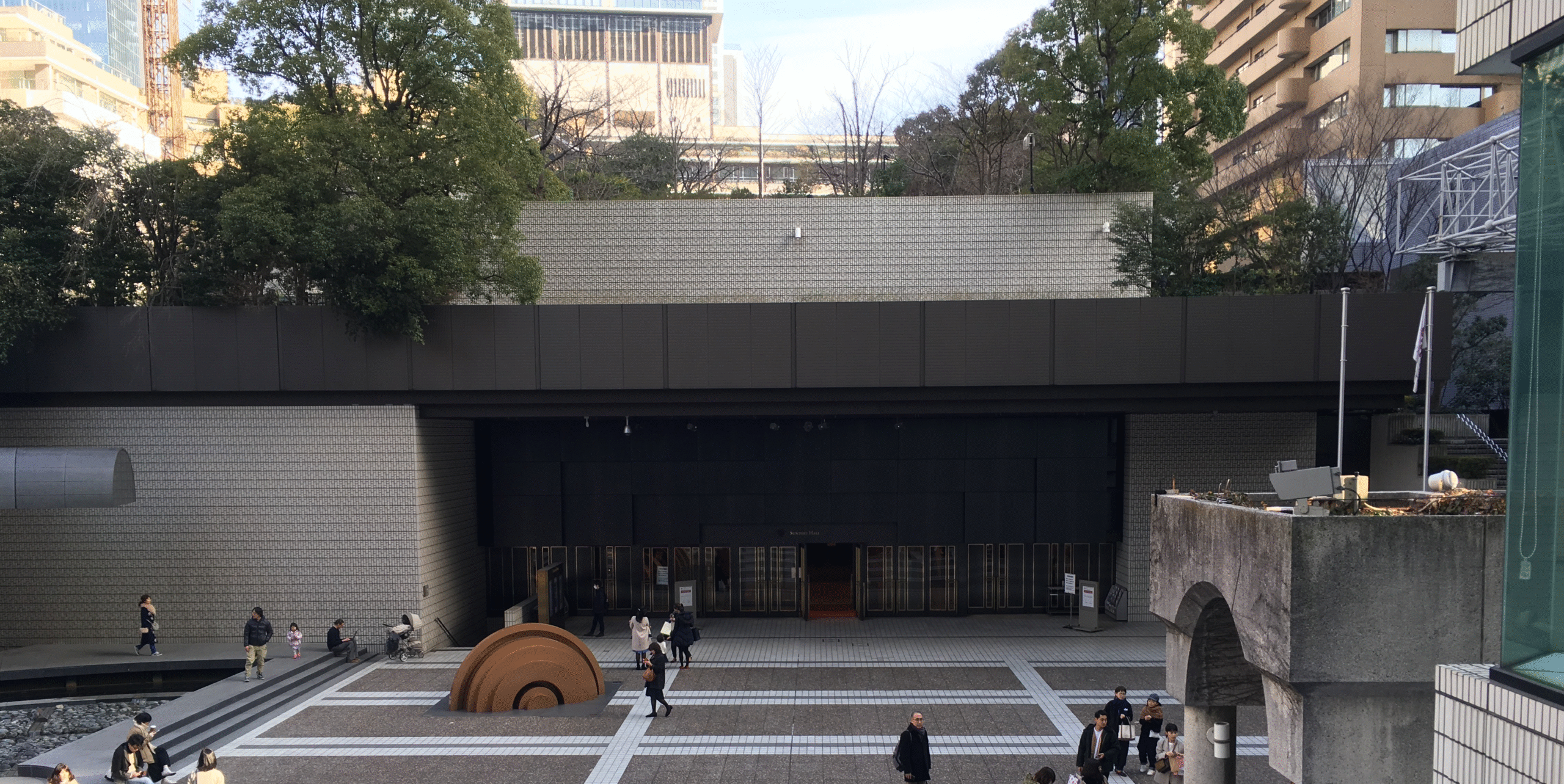

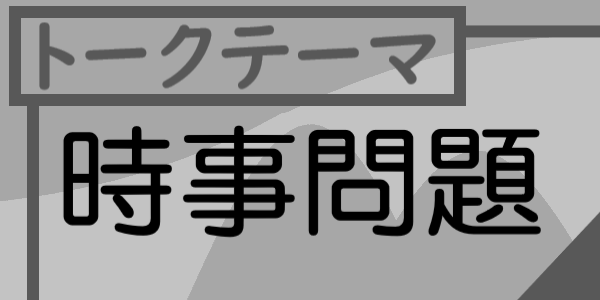

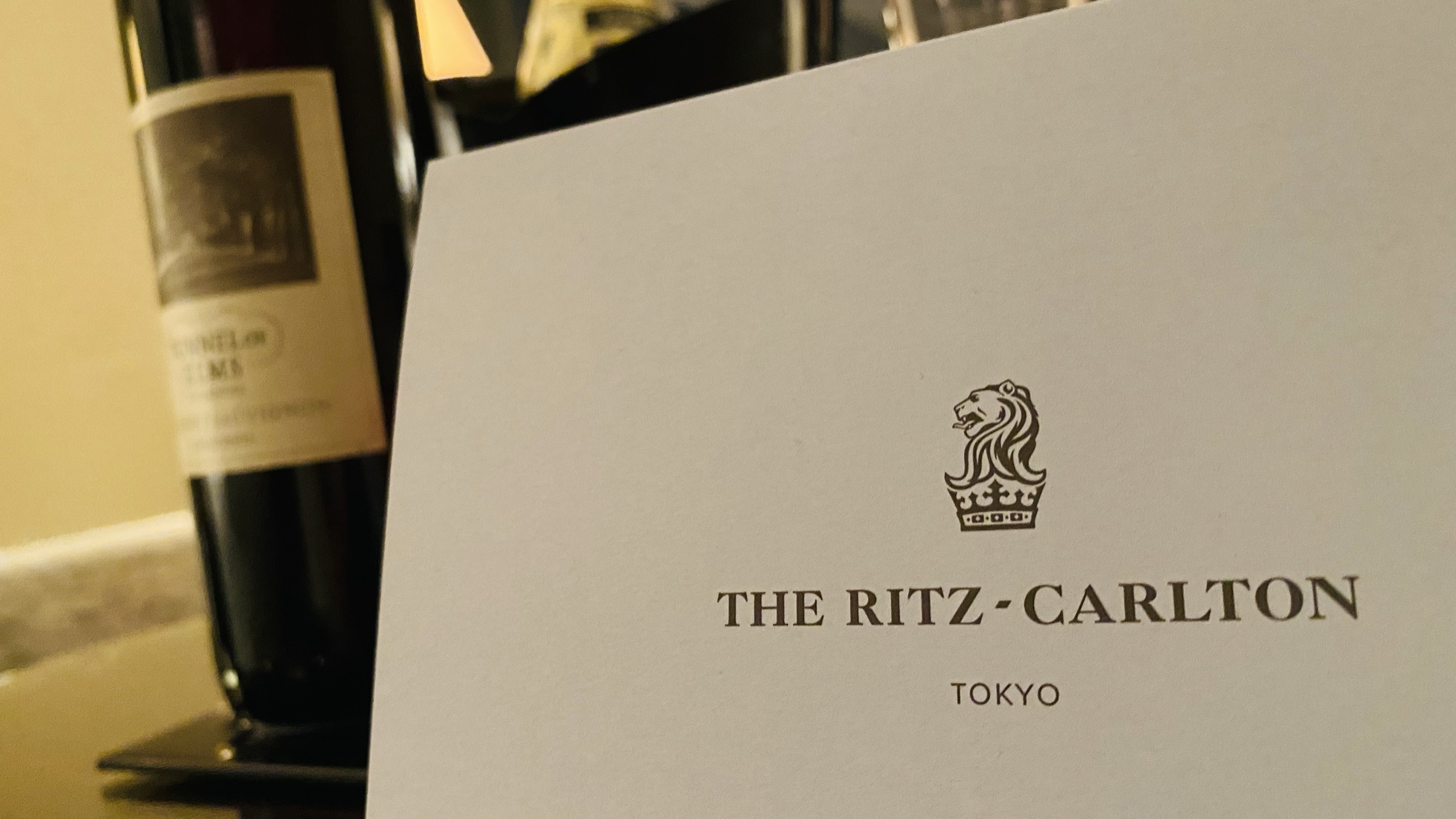
.jpg)


